

執筆者:後藤ようこ
ブログを書くコツ“社員ブログは日記じゃない”― 書きたくないブログを「営業がラクになる武器」にするには?
- 2025年07月16日
- コラム

執筆者:後藤ようこ
後藤 ようこ取締役副社長
スキル
- ランディング(執筆)
- ディレクション
- コンサルティング
大学病院で看護師として働いたのち、看護教員の資格を取得し看護教育に携わりました。
現在は株式会社ノーブランドの取締役としてウェブサイトやパンフレット制作のディレクションを担当しています。(ディレクションは20年以上の経験を持ちます。)
また、医療系の出版社で医療記事の連載をした経験があります。医療記事をはじめ、販促物に掲載する原稿作成(ライティング)も担当しています。医療知識を持っているため、医療、介護、福祉関係のお客様が多いです
これまで学んできた、教育学、人間関係論、心理学などの知識を活かし、販売促進に関わるコンサルティングも行っています。
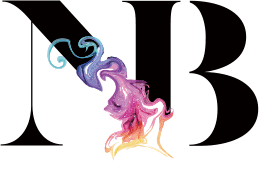
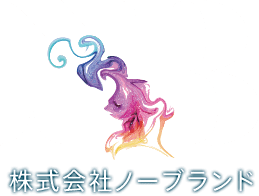
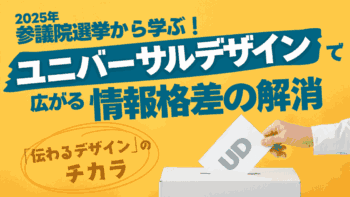 2025年参議院選挙から学ぶ!ー「伝わるデザイン」のチカラ — ユニバーサルデザインで広がる情報格差の解消
2025年参議院選挙から学ぶ!ー「伝わるデザイン」のチカラ — ユニバーサルデザインで広がる情報格差の解消 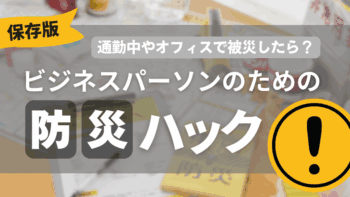 【保存版】2011年の大震災に学ぶ|通勤中やオフィスで被災したら? 仕事人のための防災ハック
【保存版】2011年の大震災に学ぶ|通勤中やオフィスで被災したら? 仕事人のための防災ハック 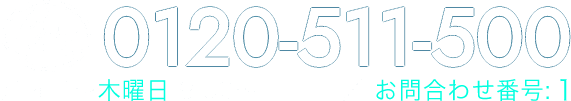
<記事の概要>
「会社のブログ、正直書きたくない」そう感じる社員がいても、それは当然のことです。ですが、少しの工夫と視点の転換で、社員ブログは“営業に効くコンテンツ”へと変わります。その方法をまとめました。目 次
1Google検索に見る“社員ブログあるある”
そんなご相談をいただくことが、よくあります。
確かに、会社のホームページを成長させるには、“良質なコンテンツをできるだけ多く、定期的に発信する”という王道を地道に続けるのが近道です。
これは今でも有効なSEO対策の基本であり、それに勝る裏技はほぼ存在しません。
とはいえ、どの企業にも専任の広報やライターがいるわけではありません。
「書ける人が社内にいない」
「文章が得意なスタッフが少ない」
――そんな中で、“社員ブログ”という形でブログを回していくのは、なかなかのチャレンジです。
だからこそ、社員に持ち回りでブログを担当してもらおう、という判断に至るのもごもっとも。
ですが、その一方で、Googleの検索窓:Googleサジェスト(*注)にこんな言葉が表示されるのをご存知でしょうか。
それだけ、「社員ブログ」に対して苦手意識や負担感を抱えている人が多いという現実があります。
実際に多くの企業ブログを見てみると、「週末に食べたラーメンが美味しかった話」や「最近ハマっている趣味」など、業務とは無関係な“日記ブログ”になってしまっているケースも少なくありません。
ですが、“営業や採用につながる”ブログに育てていくためには、少し工夫が必要です。
本記事では、
「会社のブログ、正直書きたくない…」という声に共感しつつ、
それでも会社ブログを“営業がラクになる武器”に変えるための具体策をお伝えします。
社内ブログの方向性を見直したい方、ホームページを強化したいとお考えの経営者の皆さまにとって、少しでもお役に立てば幸いです。
(*注)※Googleサジェスト:
検索エンジンで文字を入力すると自動表示される検索候補のこと。検索回数の多い語句や、関心度の高いキーワードが優先的に表示されるため、ユーザーの“生の声”を知る手がかりになります。
2そもそも、会社のブログって何のためにある?
本来、会社のブログには、明確な“役割”があります。
単なる情報発信ではなく、ビジネスに直結する以下のような目的を果たすためのものです。
つまり、会社ブログとは「情報発信の場」というよりも、デジタル営業マンの一人 。
個人ブログなら自由に好きなことを書いても問題ありませんが、
会社ブログとなれば当然、「何を書くか」「何は書かないか」を選ぶ必要があります。
その選択基準はとてもシンプルです。
上記の4つの目的に照らして、書く内容が「誰に・どんな価値を届けるか」に沿っているかどうか。
これが明確になれば、内容も“なんとなく書く”のではなく、自然と軸のあるものになります。
まずは、会社ブログは何のためにあるのか?
その原点に立ち戻って、目的や目標を言葉にするところから始めてみましょう。
書きたくない理由を、解決に変える視点
3なぜ社員ブログは“書きたくなくなる”のか?
社員が会社のブログを「書きたくない」と感じるのは、どんな理由からなのでしょうか。
自分の立場に置き換えてみると、たとえば次のような気持ちが思い当たるのではないでしょうか。
このような状態で、「順番だから書いてね」と言われても、正直なところモチベーションは上がりません。
まずは、経営者とスタッフとの温度差を理解し、歩み寄ることが大切です。
“書きたくない”と感じるのはサボりではなく、理由があるからこそなのです。
ですが、ここで諦めるのは早いかもしれません。
少しだけ工夫を加えることで、社員ブログを“成果が見えるブログ”へと変えていくことができます。
書きたくない理由を、解決に変える視点
4営業に効くブログに変える3つのコツ
ここからは、社員ブログを“営業に効くコンテンツ”に育てるための具体的なステップをご紹介します。
どれも特別なスキルは不要で、明日からすぐ取り入れられる実践的な方法です。
1. 読者ターゲットを明確にしましょう
まずは「誰に読んでほしいのか?」を明確にすることが、ブログの軸をつくる第一歩です。
これだけで文章の方向性やトーンがぐっと定まり、読み手に伝わる記事になります。
ターゲットは1つに絞る必要はありません。
複数のターゲットがある場合は、カテゴリを分けるだけでも記事の整理がしやすくなり、読み手にとっても親切な構造になります。
2. テーマは“お客様の困りごと”から考えましょう
ブログのテーマに悩んだときは、奇をてらうよりも“現場でよく聞かれること”が最良のネタになります。
それはつまり、読み手にとって「知りたかった!」と思ってもらえる価値ある情報です。
こうした内容は、営業トークや問い合わせ対応にも使えるだけでなく、
“見込み客に先回りして価値を届けられる”ブログとして、自然な営業導線にもなります。
3. 書きやすい“型”を決めましょう
「自由に書いていいよ」と言われると、かえって書きづらいものです。
そこで、あらかじめ“文章の型”を決めておくことで、誰でも安定して書ける仕組みができます。
このような“テンプレート”があれば、文章が苦手な人でも安心して書き進められます。
社内で共有しておけば、誰が書いても一定の品質が保たれます。
5オフショット記事は“悪”ではないが、SEOには貢献しづらい
こうした内容は、親しみや社内の雰囲気を伝えるという点では一定の効果がありますが、SEO(検索エンジン経由の集客)という観点では、ほとんど貢献しません。
なぜなら、「〇〇ラーメン美味しかった」だけの記事は——
といった理由から、Googleの評価軸(E-E-A-Tなど)に対してマイナスになることもあるからです。
オフショット要素を活かしたい場合は、以下のように“ビジネスとの接点を添える工夫”をすると効果的です。
こうすれば、“読まれるだけで終わらない”コンテンツとして機能します。
では、そうした“役に立つブログ”を無理なく書くには、どうすればよいのでしょうか?
そこで活用したいのが——ChatGPTです。
6ChatGPTを使えば、もっとラクに書ける
それでは実際に、ブログの文章はどのように用意すればいいのでしょうか?
テーマや内容が決まっていても、一から文章を組み立てるのは、時間もエネルギーもかかる作業です。
そこでおすすめしたいのが、ChatGPTの活用です。
「ネタが出ない」「文章がうまくまとまらない」というとき、ChatGPTを“たたき台づくりのパートナー”として使えば、作業の負担を大きく減らすことができます。
ChatGPTを使ったブログ記事作成のステップ
ChatGPTには、以下のような指示(プロンプト)を出すことで、ブログの下書きや構成をスムーズに組み立てることができます。
このように、段階的にChatGPTと対話しながら文章をブラッシュアップしていくことで、効率的かつ質の高い記事作成が可能になります。
ただし、ここでひとつ大切なポイントがあります。
それは、必ずファクトチェックと手直しを行うこと”です。
ChatGPTはあくまで「一般的で読みやすい文章」を生成するのが得意です。
しかしその反面、自社ならではの強みや、業界に特化した事実情報の表現には限界があります。
そのため、
といった視点で、最後は必ず人の手でチェック・補足を行うことが重要です。
ChatGPTは“ブログの土台を整えてくれる優秀なアシスタント”ですが、主役はあくまでも御社自身。
会社の思いや個性をしっかりと乗せることで、はじめて「伝わるブログ」になります。
うまく活用して、ストレスなく、成果の見えるブログ作成を目指しましょう。
7写真とプライバシーへの配慮も忘れずに
写真は記事全体の印象を左右し、企業の信頼感や雰囲気を視覚的に伝える重要な要素となります。
とはいえ、写真には慎重な配慮が必要なポイントも多くあります。
以下に、投稿前のチェック項目をまとめました。
写真チェックリスト
写真ひとつで、企業の信頼感や“リアルな空気感”は大きく伝わります。
だからこそ、投稿前の確認は必須。チェック体制を整えることで、トラブルのリスクを大幅に減らせます。
スタッフの顔出しには、特に注意
社員の顔写真をブログに載せる際は、本人の了承があることを大前提としましょう。
また、顔出し写真には以下のようなリスクもあります:
こうした事態に備えて、できるだけ個人が特定されにくい写真選びを心がけるのが賢明です。
それでも「社内の雰囲気をリアルに伝えたい」といった場合は、あらかじめ“退職後の写真使用について”社内でガイドラインを決めておくことをおすすめします。
(例:退職時に掲載写真を取り下げるかどうかの確認プロセスを設ける 等)
写真の印象は、文章以上に“企業の顔”になります。
リスクを理解したうえで、効果的かつ安全に活用する工夫をしていきましょう。
8まとめ:「書きたくない」を「やってよかった」に変えるには
社員ブログは「がんばってるのに成果が出ない」と思われがち。
でも、ほんの少し視点を変えれば、“営業に効く武器”になります。
これらの工夫で、「社員ブログ、書きたくない…」という気持ちも、きっと「意外と面白いかも」に変わるはずです。
9おまけ:社員ブログの成果は“見える化”で伝わるようにする
「せっかく書いても誰にも評価されない」
——こうしたモヤモヤは、社員ブログを続けるうえでよくある悩みです。
この問題を解決するためには、アクセス解析による“見える化”が不可欠です。
会社のホームページには、必ずアクセス解析ツール(例:Googleアナリティクス)を導入しましょう。
Googleアナリティクスでできること(初歩編)
アナリティクスは奥が深く、すべてを使いこなすのは簡単ではありません。
ですが、「このブログ記事が●件見られている」と日々チェックするだけでも、社員のモチベーション維持に大きく貢献します。
「見られている実感」があると、「また書いてみようかな」と自然に思えるものです。
アクセス解析の基本的な使い方や活用のコツについては、別の記事で改めてご紹介する予定です。
まずはブログの成果を“数値で把握する”ことから始めてみてはいかがでしょうか。