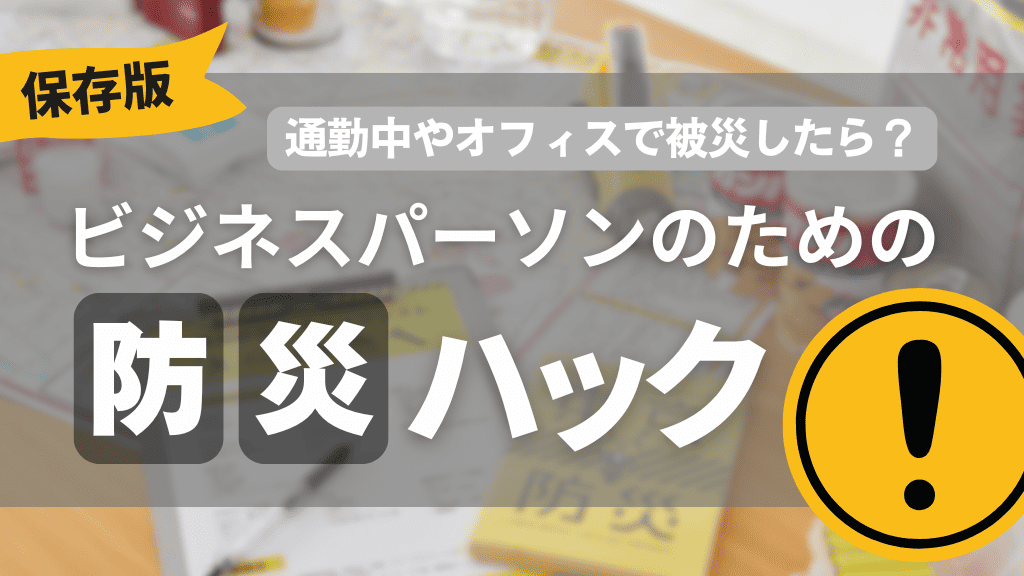

執筆者:後藤ようこ
防災【保存版】2011年の大震災に学ぶ|通勤中やオフィスで被災したら? 仕事人のための防災ハック
- 2025年07月17日
- ビジネスに役立つブログ

執筆者:後藤ようこ
後藤 ようこ取締役副社長
スキル
- ランディング(執筆)
- ディレクション
- コンサルティング
大学病院で看護師として働いたのち、看護教員の資格を取得し看護教育に携わりました。
現在は株式会社ノーブランドの取締役としてウェブサイトやパンフレット制作のディレクションを担当しています。(ディレクションは20年以上の経験を持ちます。)
また、医療系の出版社で医療記事の連載をした経験があります。医療記事をはじめ、販促物に掲載する原稿作成(ライティング)も担当しています。医療知識を持っているため、医療、介護、福祉関係のお客様が多いです
これまで学んできた、教育学、人間関係論、心理学などの知識を活かし、販売促進に関わるコンサルティングも行っています。
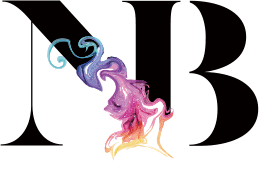
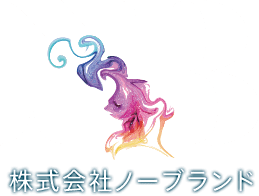
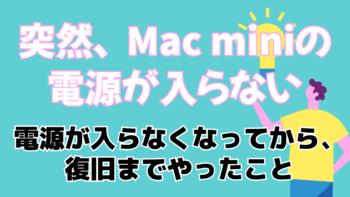 【突然、Mac miniの電源が入らない】電源が入らなくなってから、復旧までやったこと
【突然、Mac miniの電源が入らない】電源が入らなくなってから、復旧までやったこと 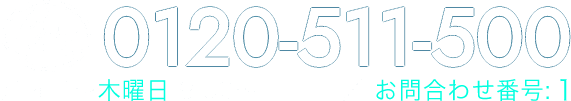
<記事の概要>
通勤中や勤務中に地震が起きたらどう動く?ビジネスパーソンが備えるべき防災グッズと、企業が整えるべき対策をまとめました。
目 次
1災害はいつやってくるか分からない
※アフィリエイト広告を利用しています
ようやく揺れも収まりつつありますが、「次は自分の地域で起きるのではないか」という不安は、簡単には消えません。
つい「自分の地域は大丈夫だろう」と思いがちですが、災害は時間も場所も選びません。
特にビジネスパーソンにとっては、通勤中や勤務中に被災したらどうするか? という備えが意外とおろそかになりがちです。
私自身、過去の経験でその現実を痛感しました。
今回のブログでは、2011年の東日本大震災での体験をもとに、「通勤中やオフィスで被災したら?」という視点で、防災のポイントをまとめてみます。
2外出先で被災したあの日
2011年3月11日、東日本大震災の日。
私はお昼すぎ、神奈川県の北鎌倉での打ち合わせを終え、横浜方面へ向かう電車に乗っていました。
天気は快晴で、春の陽ざしを浴びながら、お寺の写真を撮ったりして、気持ちのいい帰路についていたことを覚えています。
何度も乗ったことのあるJR線。
その日常が、突然の地震で一変しました。
電車は緊急停止し、その後すべての路線が運行を中止。
駅や街には不安と混乱が広がり、タクシーもバスも動かず、帰宅困難者で溢れかえりました。
スマートフォンはバッテリー切れで情報も連絡も途絶え、真冬の寒さと空腹、そしてパンプスという装備のまま、根岸駅で電車を降ろされ、そのまま横浜駅まで約7kmを歩き続けることになりました。
パンプス越しに伝わる冷たい路面の感触は、10年以上経った今でも忘れることができません。
あの経験があったからこそ、今の私の防災意識につながっているのだと感じます。
そのとき、強く思ったのは、
「災害は勤務中や通勤中にも起こる。
備えがなければ、体力も情報も、あっという間に尽きてしまう」
という現実でした。
3ビジネスパーソンが持っておくべき6つの備え
そしてその習慣は、14年以上経った今でも続いています。
単なる「非常時の保険」ではなく、災害が起きても安全を確保し、連絡を取り続け、冷静に動ける状態を保つための道具として意識するようになったのです。
これらのアイテムは、命を守るのはもちろん、会社員として業務を続けたり、家族との連絡を絶やさないためにも欠かせません。
ここからは、2011年の震災での体験を踏まえ、ビジネスパーソンが備えておくべき6つのポイントについて紹介します。
オシャレなのに”お得で高機能”な防災セット
41. モバイルバッテリーとケーブル
情報収集や安否確認、地図アプリやSNSでの連絡が止まってしまえば、状況を把握できず、家族や会社とも連絡が取れません。
2011年の震災時、私自身はモバイルバッテリーを準備していなかったため、電車を降ろされた直後にスマホの充電が切れてしまいました。
その結果、連絡手段は公衆電話しかなく、当時まだ残っていた公衆電話には長蛇の列ができていました。
こうした経験からも、モバイルバッテリーと充電ケーブルは必須の備えだと実感しています。
出先で被災した場合は、スマホを省エネモードで使い、必要最低限のやり取りだけに抑える工夫と併せて、必ず持っておくことをおすすめします。
公衆電話
私は、公衆電話が使えるようにテレホンカードも携帯しています。万が一、小銭がなかった場合などにはテレホンカードが役立ちます。財布にテレホンカードを入れておくのもいいでしょう。
52. 500mlの飲料水と軽食(カロリーメイトなど)
飲みかけであっても構いません。「常に水を持っている状態を習慣化する」 ことが大切です。
加えて、ソイジョイやカロリーメイトなど、軽めで保存がきく軽食を1つ入れておくようにしています。
震災当日、私は帰宅途中にコンビニに立ち寄りましたが、食料品はすでにすべて売り切れていました。通常ならすぐ補充されるはずの商品も、大災害時には供給が止まり、手に入らなくなります。
7〜10kmの徒歩移動でも、想像以上に体力を消耗します。
最低限の水とエネルギー補給ができるものを常備しておくことで、動ける状態を保てます。
バッグの中が重くならないよう、持ち運びやすい軽量なものを選ぶのがポイントです。
水分摂取は計画的に
大震災のときには、トイレを利用することが極めて困難になります。
しかし、必要だからといって我慢し続けるわけにもいきません。水分を取りすぎればトイレが近くなり、逆に水分を控えすぎれば脱水のリスクが高まります。
非常時には、事前にトイレの位置を確認しながら、計画的に水分を摂取することが重要です。
その上で、1~2回分の携帯用の簡易トイレや、手や体を清潔に保てるウエットティッシュを持ち歩いておくと安心です。長時間の移動や待機でも、衛生面の不安やストレスを大幅に減らせます。
63.歩きやすい靴や替えのソックス
本来であれば、軽量で折りたたみできるスニーカーやサンダルを携帯するのが理想です。
歩行時の負担を大きく減らせるからです。
とはいえ、常にカバンに入れて持ち歩くのは現実的ではありません。そこで、外出時はできる限り自分の足に合った、歩きやすい靴を選ぶことを心がけています。パンプスを履く場合でも、ヒールが低めで柔らかい素材のものを選ぶだけで、移動時の疲労感がかなり違います。
さらに、靴下を1足バッグに入れておくこともおすすめです。靴擦れや足の冷えを軽減でき、災害時の長時間の徒歩移動でも足を守れます。
加えて、オフィスに歩きやすい靴を1足常備しておくのも安心です。緊急時、仕事用の革靴やパンプスから履き替えられるだけで、移動の負担を大きく減らせます。ヒールの高い靴は近場の外出のみにするようになりました。
リュック
震災前までは手に持つタイプのカバンを使っていましたが、以降は極力リュックを選ぶようにしました。今はビジネスシーンでも使えるデザイン性の高いリュックが豊富です。肩への負担が少なく、収納力があり、常に必要なアイテムを携帯しやすいのがメリットです。
74.トイレをすませてから電車にのる(エレベーターも)
しかし、必要だからといって我慢し続けるわけにもいきません。
水分を取りすぎればトイレが近くなり、逆に水分を控えすぎれば脱水のリスクが高まります。
私自身、2011年の震災を経験してから、電車やエレベーターに乗る前には必ずトイレを済ませるようにしています。たとえ行きたくなくても、閉じ込められたときの不安を考えると、事前にリスクを減らすことが重要だと感じたからです。
先日の地震の際も、ほとんど水分を摂らなかったためトイレの心配はしませんでしたが、もし閉じ込められた時に行きたくなっていたら……と考えると、今でもぞっとします。
もちろん、1~2回分の携帯用の簡易トイレを持ち歩くことも有効な備えです。
しかし実際に使うシチュエーションは精神的にも負担が大きいため、できるだけ事前にトイレを済ませるなど、回避策を取りつつ備えることをおすすめします。
85. 使い捨て手袋(ビニール手袋)
理由は、もし大きな地震で被災者が出た場合、人命救助の場面に立ち会う可能性があるからです。
大規模災害時には、いやがおうでも周囲と助け合わなければ、危機を乗り越えることはできません。実際にその状況になったら、おそらくためらう暇もなく体が動いてしまうでしょう。
そんなとき、できるだけ自分の身を守りつつ、救助に関わるための最低限の備えとして、ビニール手袋を持ち歩くようになりました。手袋があることで、怪我や感染症のリスクを軽減しながら、安心して人を助けることができます。
96. SNSでのつながりを確保する
東日本大震災の直後、電話もメールもSMS(スマホのチャット)も、長時間まったくつながりませんでした。
被災した多くの人が同時に電話回線を使ったことで、通信障害が長く続いたのです。
しかしそのとき、唯一つながり続けたのがSNSでした。
TwitterやFacebookを通じて家族や知人と連絡を取り合えただけでなく、突然の災害で社内に取り残され、不安でいっぱいだった私に、多くのフォロワーが声をかけてくれました。その言葉が、どれだけ心の支えになったか、今でも鮮明に覚えています。
それ以来、私は家族とも「万一の時にはSNSで連絡が取れるようにしておく」ことを決めています。
SNSは、物理的なツールと同じく“災害時のライフライン”として活用できる備えの一つです。
10その他、私のバッグに入っている携帯品のご紹介
いつも外出時に持って歩くリュックの中に入っている、私の携帯品をご紹介いたします。
11企業として取り組むべきこと
個人での備えに加えて、企業としての防災対策も欠かせません。
災害が発生した際、社員の安全を守るだけでなく、事業を継続させるためには、日頃からの準備が不可欠です。
以下に、企業が最低限取り組むべきポイントをまとめましたので、ぜひご参考ください。
オシャレなのに”お得で高機能”な防災セット
121.オフィスへの非常食・飲料水・毛布の備蓄
私自身も2011年の震災でJR線が完全に止まり、翌日まで復旧しませんでした。
代わりにバスを利用しましたが、1時間で数メートルしか進まない状況でした。
交通網がストップするということは、社員が自宅に帰れないことを意味します。
徒歩での帰宅以外、方法がなくなるのです。
だからこそ、最悪の場合は会社内で社員全員が宿泊できる準備を整えておくことが理想です。
男性・女性それぞれの比率や必要な物資、プライバシーに配慮した宿泊スペースの確保も重要です。
132.全社員が使える安否確認ツールや連絡網の整備
電話回線は災害時に混雑してつながりにくくなるため、チャットツールやメールを使った連絡ルールを平時から決めておきましょう。
社員がつながるSNSがあれば便利ですが、そうでない場合でも、誰が誰とつながっているのか、どの順序で安否確認を回すのかを事前に打ち合わせておくことが大切です。
特に、異性の上司と部下のペアでは連絡が取りづらい場合も考えられます。
その場合は、管理職を中心に、同性の上司や同僚を介して連絡を取り合う仕組みを作っておくと安心です。
なお、2011年の震災時には、電話はつながらなくてもメールは届いたという事例が多くありました。
最低限、E-mailでの安否確認がスムーズにできるよう、社内でのルール化をおすすめします。
主なSNS
143.避難ルートや帰宅方針を明文化したBCP(事業継続計画)の策定
出勤前に震災が発生した場合の出社義務など、社員一人ひとりが判断に迷うケースも想定されるため、平時からルールを決めて周知しておきましょう。
さらに、緊急時に出社できない場合でも、最低限の業務をリモートワークで継続できる体制があれば、顧客対応の混乱を減らせます。現実的に難しい面もありますが、無理のない範囲で代替手段を検討しておくことが望ましいでしょう。
15まとめ:備えが「安心」につながる
大きな地震や災害は、いつ起こるかわかりません。
日頃から必要な物を揃えておくことが、冷静な対応と安全の確保につながります。
特にビジネスパーソンにとっては、外出先や通勤中、帰宅中に被災するリスクも無視できません。
平時から備えておくことで、もしもの時にも慌てず動けるようになります。
最後に、必要な防災グッズがひと通り揃った「防災バッグ」をご紹介しておきます。
リュック一つを準備しておくだけでも、大きな安心感につながります。
年に一度は中身を見直し、使用期限やバッテリーの状態を確認しながら、すぐに持ち出せる状態をキープしておきましょう。
【防災士&消防士監修】いざというときに備える充実の44点セット あかまる防災