

執筆者:後藤ようこ
万博ロゴが最強だった印刷リスクの視点から見て解説!大阪・関西万博ロゴデザインが最強だった。
- 2025年10月08日
- ノウハウ

執筆者:後藤ようこ
後藤 ようこ取締役副社長
スキル
- ランディング(執筆)
- ディレクション
- コンサルティング
大学病院で看護師として働いたのち、看護教員の資格を取得し看護教育に携わりました。
現在は株式会社ノーブランドの取締役としてウェブサイトやパンフレット制作のディレクションを担当しています。(ディレクションは20年以上の経験を持ちます。)
また、医療系の出版社で医療記事の連載をした経験があります。医療記事をはじめ、販促物に掲載する原稿作成(ライティング)も担当しています。医療知識を持っているため、医療、介護、福祉関係のお客様が多いです
これまで学んできた、教育学、人間関係論、心理学などの知識を活かし、販売促進に関わるコンサルティングも行っています。
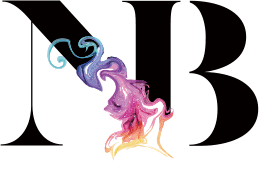
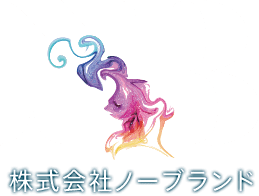
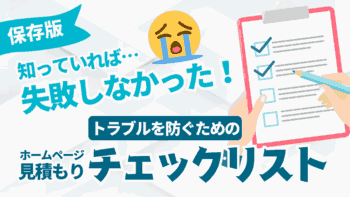 【保存版】知っていれば失敗しなかった!ホームページ見積もりトラブルを防ぐためのチェックリスト(Wordダウンロード付き)
【保存版】知っていれば失敗しなかった!ホームページ見積もりトラブルを防ぐためのチェックリスト(Wordダウンロード付き) 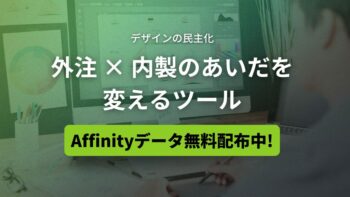 【afデータ無料配布】Affinity無料化で社内で販促物が自由にデザインできる時代に!
【afデータ無料配布】Affinity無料化で社内で販促物が自由にデザインできる時代に! 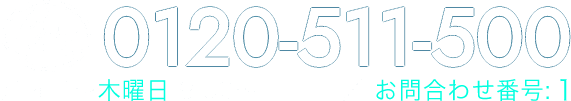
<記事の概要>
大阪・関西万博は盛況裡に閉幕。賛否のロゴは少色・高コントラスト・面構成で印刷運用に強く、単色・縮小・多方式展開でも崩れにくい“やさしい”設計だった。大阪・関西万博ロゴデザインを印刷リスク視点で解説。目 次
1大阪・関西万博のロゴと「ミャクミャク」も成功だった
2025年4月13日から184日間にわたって開催された 2025年日本国際博覧会(EXPO 2025/以下「大阪・関西万博」) が閉幕しました。
万博会期中の一般来場者数の累計が2557万8986人。
各パビリオンは連日盛況で、総じて“成功裡の着地”したといえるでしょう。
万博のテーマは以下の通りでした――
Designing Future Society for Our Lives
みなさんは、大阪・関西万博には行ってみましたか?
それぞれ、様々な感想をもった大阪・関西万博だったのではないでしょうか?
さて、本コラムでは、グラフィックデザインを扱う我々の立場から、賛否を呼んだロゴマークに焦点を当てて解説してみたいとおもいます。
まず、見た目の好き嫌いは一旦脇に置き、デザイン × 印刷・量産・多用途展開という“現場目線”で評価します。
結論から言えば、
あのロゴマークは極めて“やさしい”設計だと感じました。
ここでの“やさしい”とは、
という意味です。
日々、商業印刷やグッズ制作に携わるデザインチームの立場から、なぜ最終案が現場で強かったのかを掘り下げてみたいと思います。
企業や自治体でロゴを決めるご担当者の参考になるようまとめました。
ぜひ最後までお読みください。
以下の視点で解説していきます。
2最終候補の5つの案について
まずは、ロゴマークの候補となった5つの案についてです。
2020年8月に、大阪・関西万博のロゴマーク最終候補作品5作品が発表されました。
候補作品は以下の5案です。
それぞれ、個性的で素敵なデザインですが、この中で実際の万博のロゴマークに採用されたのは「E案」です。
ちなみに、E案のデザインコンセプトは以下の通りでした。
いのち輝く未来社会のデザイン、というテーマに沿ったインパクトのあるデザインで、このロゴマークはいろんな意味でも最強だったので、以下に解説していきます。
3色数は“お金”と“事故率”に直結します
今回決定した「E案」が他の案と決定的に違ったのは色数です。
「E案」は「赤」「青」の2色もしくは「白」も含めた3色構成であることがポイントです。
ベース枠が「赤」というだけで、他のロゴ作品と比べてもかなり汎用性があり、これだけでロゴとして採用されやすい決定打にあたると感じました。
ここからは【視認性】と【印刷コスト】という面でさらに深堀りしてみましょう。
視認性 ー白地以外で見えにくくなる可能性は無いか?
ロゴマークを考える時に、もっとも気をつけたいのが視認性です。
たとえば、下記の画像のように、下地に白以外の別の色を配置した場合に、どのような見え方になるかが注目ポイントです。
選ばれた「E案」は、下地が黒でもグレーでも、十分な視認性があります。
下地による影響や、遠くから見た時の印象という面でも、「E案」はシンプルな形状で、かつコントラストがはっきりしているロゴデザインです。
このようなロゴマークはどんな使われ方をしても視認性が高いです。
逆に、少しでもゴチャっと潰れて見えてしまうものは、使い方に注意が必要です。
他の案で比較してみましょう。
単色ロゴ使用での展開も想定しておく
行政や業者間などで、簡単な資料を作るときは、白黒印刷でプリントをすることもあるでしょう。
スタンプラリーなどで活躍する、単色のハンコも作る場合もあります。
様々なノベルティグッズを作る場合に使いやすいか
もう一つ、ロゴマークを考える上で大事なポイントがあります。
特色*を使用したノベルティや衣類(シルクスクリーン)などに用いる場合の使い勝手です。
このようなノベルティを作る場合、色数が増えるほど金額が高くなるというケースが多いです。
フルカラーよりも特色や白黒の方が安価になります。
分かりやすいのは、刺繍やワッペンです。
帽子やポロシャツなどのオリジナルグッズを作る際に、衣類には刺繍をしたりします。
刺繍でロゴマークを表現する際に、複雑なロゴマークは業者泣かせです。
もちろん、刺繍に限らず、オリジナルグッズを作る場合に、ロゴマークが再現しやすいかどうかも、ロゴマークを決定する際の評価基準となります。また、カラーで印刷せざるを得ないマークよりも、単色で表現しやすいマークの方が安価にしあがる場合があります。
そういう意味でも「E案」のようなシンプルなフォルムは有利であると考えられます。
*特色とは:
「特色(スポットカラー)」は、CMYKの混色ではなくPANTONEやDICなどで規定された“その色”のインキを1色ずつ刷る方式です。
ブランドカラーの厳密再現やCMYKで出にくい鮮やかな赤・深い紺・安定したグレー、金銀・蛍光・白インキなどの特殊効果に向きます。
網点に頼らないため発色がクリアでロット間の色ブレが少なく、細線や小文字のエッジも綺麗に出る一方、色数分だけ版・洗浄・段取りが増えてコストは上がり、写真主体や多階調表現には不向きです。
使うならロゴ・封筒・単色ツール・金銀や白を使うパッケージなどがおすすめです。
要するに「色を厳密に合わせたい/特殊色を使いたいなら特色」、それ以外はCMYKが基本、と覚えると判断が速くなります。
4印刷エラーのリスクの視点からロゴマークを考える
しかし、一方的に「E案」は良くて他のマークはダメ!という訳ではありません。
それぞれ、いろんな魅力があり、個性的でクリエイティブな作品だと思います。
しかし、商業デザインとして活用する際には、使用目的をシビアに考えて行く必要があるという点を踏まえておきたいです。ワンポイントで使うだけなら、どの案も問題ありませんが、さまざまな方式の印刷やグッズ制作となると印刷エラーのリスクやコストを考えなければなりません。
この章では、印刷エラーのリスクから「E案」を考えてみます。
ロゴマークを確実に再現できるか
こんな経験はありませんか?
ーパソコン画面上では読めていた文字でも、いざプリントアウトするとインクが滲み文字が潰れてしまった。
実はこれは、プロの現場でも同じことが起きることがあります。
よって、ロゴマークのサイズを横幅20mm位に小さくしたときに、細かい表現がぼやけて見えないか確認してみましょう。線がガタガタになりそうと思ったら要注意です。
版ズレのリスクを避けられるか
さらにオフセット印刷の場合は、版ズレという印刷リスクがあります。
版ズレ*とは、CYMKの4つの色版が少しずれることです。
印刷では、0.5mmずれただけでも近接した色とぶつかり細かいエッジが潰れてしまいます。
印刷はアナログであると再認識させられるエラーの1つです。
「それならば、印刷の上手い職人がいるところに頼めばいいのではないか?」
「失敗したら、もう一回刷り直ししてもらえばいいのではないか?」
と思われがちですが、ビジネス上では予算と時間が決まっており、それに関わる労力も考えなければなりません。
したがって、あえてリスクを負いそうなデザインを選択する必要はありません。
以上をふまえて、E案以外の最終作品を簡単に比較してみます。
B案は細かい泡沫状の部分が細かすぎて気になります。
C案はフォルム自体は優秀ですが、やはり三角に重なる部分が気になります。
D案は2色づかいで表現している、細い線が気になります、(表現できるか)
一見、C案は好ましく感じましたが、細かい白抜きが「E案」よりも複雑で、唯一のウィークポイントのように感じました。
*版ズレとは
版ズレ(見当ズレ)とは、多色印刷で各色の版の位置合わせがわずかにズレる現象で、たとえ0.1–0.3mmでも白いフチや色の二重線、細部の欠け・潰れ、色の濁りとして現れます。原因は用紙の伸縮や湿し水による寸法変化、布や樹脂など素材のたわみ、機械や版・ブランケットの伸び、搬送の斜行、乾燥差や静電気など。
5結論:やっぱり、E案が強い
満を持して、大阪・関西万博は閉幕しました。
今になってみてロゴマークを改めて見てみると「E案」が選ばれたのは必然なのかもしれないと思います。
結果として、一番使い勝手のよいロゴが最終決定だったということです。
シンプルなのに万能。
どこか愛嬌とオリジナリティがある。
大阪・関西万博ロゴマークと、イメージキャラクターのミャクミャクは、そんな印象を残して終わりました。
ロゴマーク一つを解説するだけで、記事が1本書けるくらいに大切なことを教えてくれました。
これからロゴを決定していく際には、見た目やフィーリングだけではなく、印刷方法や運用面から視点を加えて、ジャッジすることも考えてみてください。
何かご不明な点やご相談ごとがありましたら、お気軽にご相談ください。