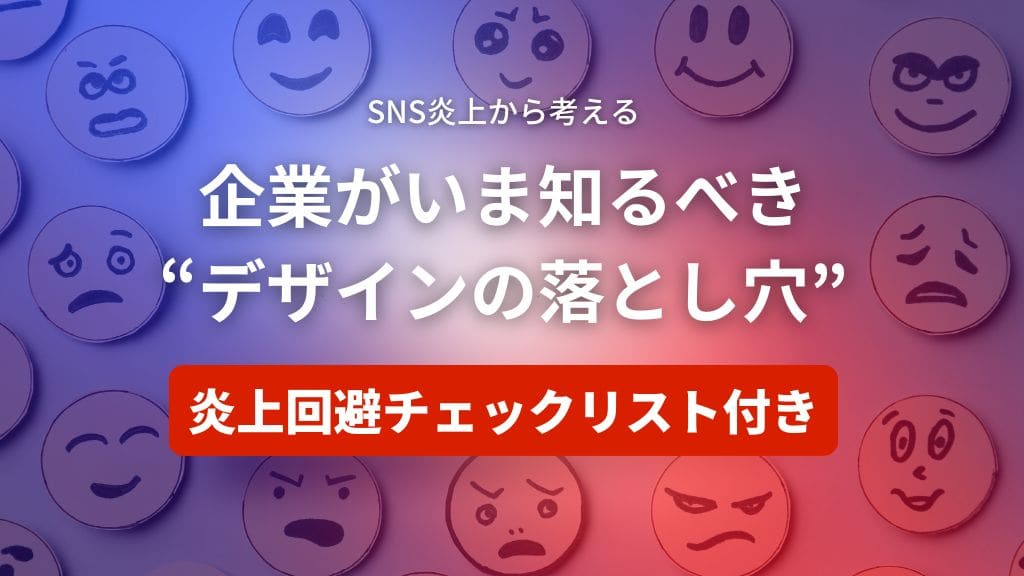

執筆者:石川浩子
炎上リスクヘッジ説明できるデザインが組織を守る。日本代表キービジュアル騒動から考える炎上リスクマネジメント
- 2025年11月20日
- コラム

執筆者:石川浩子
石川 浩子チーフデザイナー
スキル
- DTPデザイン
- クライアントコミュニケーション
- プロジェクト進行
- 校正運用
- 画像処理(色補正、トーン統一、切り抜き、ノイズ低減、圧縮最適化)
- 配色設計・カラーマネジメント
- 印刷知識
NETA
宣伝のネタ帳
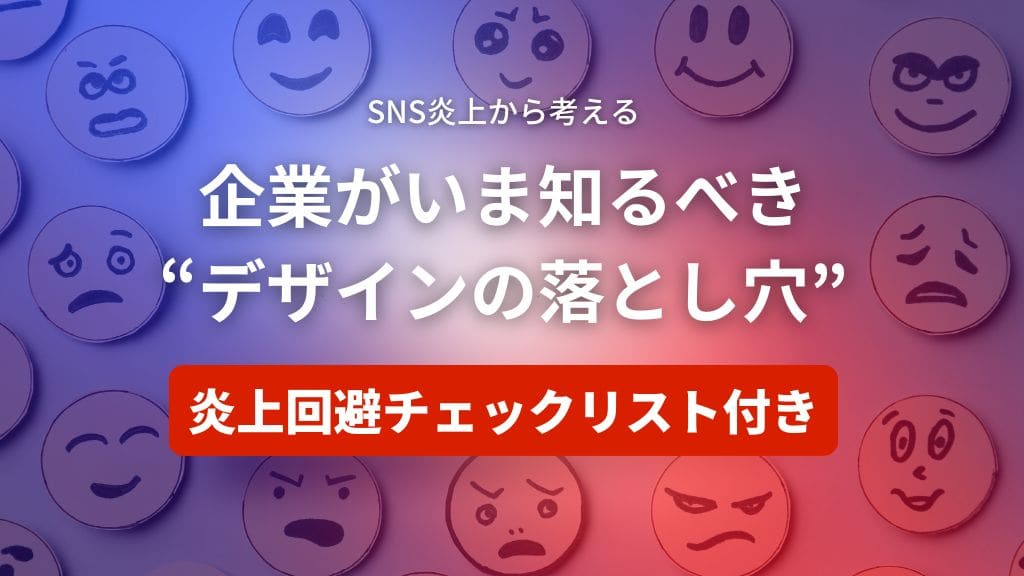

執筆者:石川浩子

執筆者:石川浩子
スキル
EVENT
カレンダーは横にスクロールしてご覧ください。
TEL.0120-511-500月〜木 9:00〜18:00
お問合せ番号:1
<記事の概要>
とあるデザインの炎上を起点に、意図より“連想”が先に立つ時代のリスクと、炎上を減らすチェック視点を整理。目 次
1「日本サッカー協会(JFA)キービジュアル炎上」の経緯
先日、日本サッカー協会(JFA)が発表したサッカー日本代表の「キービジュアル」が、SNS上で大きな波紋を呼びました。
(詳しいニュースはこちら➡記事を読む)
問題となったのは『サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー』のキービジュアル。
その1枚の画像を巡り、アンバサダーに就任したグループの背景や、配色・構図が隣国の国旗を連想させるという指摘などが重なりSNSで大炎上することとなりました。
その後、またたくまに、日本サッカー協会(JFA)は公式サイトにて『サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー』のキービジュアルの変更を発表。
短期間のうちにキービジュアル差し替えを余儀なくされました。
SNSで炎上する具体的な要素は、白・赤・青の色使いと幾何学的な線が、あたかも隣国の国旗を想起させる構成になっていた点でした。
ネット上では、「なぜ日本代表なのにこの配色なのか」と物議を醸すこととなったのです。
この一連の出来事は、デザインの“意図”よりも“受け取られ方”が先に動く時代を象徴する事例と言えるでしょう。
本ブログでは、この騒動をテーマに、中小企業が考えるべき販促物デザインにおける注意点についてまとめましたので、ぜひお読みください。
2「センスの問題」ではなく「受け取られ方」
この『サッカー日本代表』のキービジュアル炎上問題よりも前から、デザインに関する炎上騒動はたびたび起きています。
時に、デザイン関連の炎上においては、
などなど、一般消費者の主観に基づくコメントの批判が沸き起こることがあります。
そして、今回の日本代表キービジュアル炎上騒動は、本質的には “どのように受け取られたか” の問題だったと言えます。
当然ながら、制作側は「日本代表をいっぱい応援してもらいたい」という意図があったはずです。
しかし、見る人の一部は「隣国っぽい」「なぜこの国旗のイメージ?」と感じてしまいました。
誰かの発信を発端に、「そうだ、そうだ」と、その受け取り方がSNSで拡散し炎上するという形になっていきました。
つまり、デザインの良し悪しよりも、「どんな連想を起こしてしまったか」が結果を左右したと言えるでしょう。
ココがポイント!
炎上の火種は“作り手の意図”よりも“受け手の連想”で起こり、不特定多数の多くの意見が一同に集まり意見が交錯する傾向が多いです。
3どこが炎上ポイントだったのか?
まずは事実関係をできるだけ感情を入れずに整理してみます。
大まかな流れ
1. 配色や構図が、隣国の国旗を想起させると指摘された
2. 「なぜ日本代表なのにその配色なのか?」という疑問や批判がSNSで広がった
3. その声を受けて、JFAが「意図的ではない」とするコメント表明やビジュアル変更など対応に追われた
ここで見えてくるのは
制作側が「隣国を意識して作った」かどうかは定かではないにもかかわらず、「そう見える」という声が拡散したことで、対応を迫られた。という点です。
制作社の意図は、明確な声明がでていませんので、本ブログでも、本意については触れません。
あくまでも客観的に見えてくるものだけ論じていきたいと思います。
問題の要点整理
これら、複数の要点が複雑にからみあって炎上につながる典型例になりました。
ココがポイント!
「意図していない連想」でも、特定のテーマ(国・政治・宗教など)に触れると、一気に炎上リスクが高まる。
4他人事ではない!「意図」より「連想」が先に立つ時代
ただし、ここまで読んだだけでは
「いや、うちはそんなセンシティブなことは扱わないから大丈夫では?」ーー
と思われるかもしれません。
しかし、日常的なビジネスでは「意図しない連想」が問題になるケースが増えています。
よりリアルに想像しやすい4つのケースを紹介します。
事例1:アーティストの衣装が、戦争などをイメージさせたケース
あるアーティストがステージで着ていた衣装が、
・キノコ雲を思わせるシルエットや柄
・軍隊の制服のような装飾
に似ているという炎上がありました。
これらによって、特定の戦争や歴史的出来事を連想させるとして批判されたケースがあります。
制作側に政治的な意図があったかどうかは別として、「戦争をファッション化しているように見える」という受け取り方が広がってしまいました。
ここでのポイントは、
後で、「メッセージを込めたつもりはない」と言い訳をしても、連想される歴史的・社会的イメージが強すぎると、それ自体が“メッセージ”になってしまいます。
事例2:「0円」と大きく書かれた広告が、実は高額サービスだったケース
特に、サブスクサービスなどでよく問題になるのが、
「0円」「無料」だけが強く印象に残るデザインです。
この場合、「補足説明もちゃんと入れたのに」と制作側は言いたくなりますがーー
見た側からすると「0円と勘違いさせるような見せ方だ」と感じてしまいます。
『何が書いてあるか』だけでなく、『どこに・どのサイズで・どう配置されているか』という点も重要になってきます。
事例3:高級サービスに“完成度低いAI画像”を使ったケース
最近増えているのが、高額サービス × チープな生成AI画像 の組み合わせで起きる炎上です。
これらは、画像そのものよりも、
「細部の違和感に気づいていない会社」
「目が行き届いていない会社」
という印象をユーザーに与えてしまいます。
結果として、「この会社、本当にクオリティにこだわっているのだろうか?」という疑念を生むことに・・・
高価格帯のサービスほど、ビジュアルの“緻密さ”が信頼の裏付けになることを意識しておきたいところです。
事例4:災害直後の“炎・津波”モチーフが不適切と受け取られたケース
最後に、判断が難しいのが「タイミングの問題」です。
この場合、デザインそのものが悪いとは限りません。
平時なら問題にならない表現でも、「いまは避けるべき時期だった」というだけで炎上することがあります。
市民の深層心理に配慮して、広告を打ち出すのを延期したり、内容を見直す必要があります。
5気をつけたい「炎上しにくい」3つの視点
ここからは、実際にパンフレットやポスターを作るときに役立つ“3つの視点”を整理します。
難しい理論ではなく、「会議でそのまま使えるチェック観点」として読んでみてください。
国旗・宗教・政治を連想させるモチーフになっていないか?
まず押さえておきたいのは、「特定の国・宗教・政治」を連想させる組み合わせです。
これらが偶然でも、ある国旗や政治運動と似てしまうことがあります。
もちろん、「一切使ってはいけない」という話ではありません。
ただ、
といった文脈では、より慎重に見ておく必要があるでしょう。
SNSで“画像1枚だけ切り取られても”誤解を生まないか?
炎上の多くは、画像1枚が単独で広がるところから始まります。
そこで有効なのが、制作の終盤に
「このデザインを、画像一枚だけで見たらどう感じるか?」
と、あえて“説明なしの状態”で眺めてみることです。
を想像してみましょう。
社内に「ちょっと待って」と言えるチェック体制があるか?
どんなに優秀な担当者でも、自分の作ったものには盲点が生まれます。
制作担当者「これは大丈夫だろう」と思っていても、別部署の人が見ると「ちょっと危ないかも」と感じる。その“違和感”を拾えるかどうかが、炎上回避の分かれ道になります。
そのためには、
といったプロセスを、あらかじめ“ルール化”しておくことが効果的です。
ココがポイント!
「優秀な人」に一任するよりも、「別の目線が必ず入る仕組み」を作るほうが、炎上リスクは確実に下がります。
6すぐ使える“炎上回避チェックリスト”
ここまでの話を、実務で使いやすい形に落とし込んでみましょう。
リリース前・印刷前に、チームでサッと確認できる 7つのチェック項目 です。
こちらからダウンロード
チェック項目リスト(7個)
OK/NGの基準
OKな状態
・説明文がなくても、誤読される可能性が比較的低い
・社内でチェックした際、「ここはやめておこう」という明確な懸念が出ていない
・もし質問されたとしても、「なぜこの表現なのか」を自信を持って説明できる
NG寄りの状態
・社内で「ちょっと危ない気もするが…まぁ大丈夫だろう」とモヤモヤしたまま進んでいる
・「なんとなく不安だけど、作り直しが大変なので見なかったことにする」空気がある
・パンフを見せたときに、数人が同じ違和感を指摘しているのに対応されていない
迷ったときは、どうすればいいか?
・思い切って表現を変える(色や写真を差し替える)
・「今回は使わない」という判断をする
・制作会社に相談し、「第三者の目+専門的な観点」で整理してもらう
特に制作会社は、他社事例を多く見ていますので、「どこまでなら許容されるか」の感覚があります。また言語化が難しい違和感を、見つけて別の提案をしてくれるでしょう。 デザインだけではなく、“判断のパートナー”としても相談してみるのをおすすめします。
ココがポイント!
チェックリストは「完璧な安全」を保証するものではありませんが、
「気づこうとする姿勢」がある組織であること自体が、リスクを大きく減らします。
7まとめ:「炎上リスクを下げるのは、“気づきと説明”の積み重ね」
ここまで見てきたとおり、炎上リスクを完全にゼロにすることは難しいかもしれません。
ただし「意図よりも連想が先に立つ時代である」という前提を理解しておくだけで、制作判断は大きく変わってきます。
特に、国旗、宗教、政治、災害表現 といった、感情を揺さぶりやすいモチーフは慎重に扱う必要があります。
また、「画像1枚でどう見えるか」、そして「今このタイミングで適切か」を意識するだけでも、誤解の芽はぐっと減らせるでしょう。
そして何より大切なのは、「なぜこの色なのか」「なぜこの構図なのか」「なぜこの写真なのか」を、社内で自分たちの言葉で丁寧に説明できる状態にしておくことです。
説明できるデザインは、多少の批判が起きても社内で守ることができ、社外に対しても誠実に理由を伝えられます。これは、長くブランドを育てるうえで大きな安心感につながります。
今回の炎上で「攻撃したり、嘲笑ったり」してしまっていませんか?
炎上が起きたとき、つい外野になって眺めてしまいがちです。
しかし、こうした出来事こそ「もし自分たちが同じ立場だったら?」と考える良い機会にもなります。
知識量や価値観に差があることは当たり前です。
何よりも、デザインが差し替えになった際のデメリットを想像してみましょう。
印刷してしまった場合は、刷り直しが必要になります。
印刷物を郵送で配布してしまった場合は、再送付などのリスクもあります。
印刷料金のみならず、配布にかかった費用も倍かかるデメリットを生じるリスクがあるのです。
これらは、対岸の火事ではなく、自分たちの身に起こる可能性のあるリスクとして用心しておくことが重要です。
たとえば、- 若手は、歴史・文化の背景について上司や身近な大人に質問してみる
- ベテラン層は、若い世代の価値観やSNSの感覚を共有してもらう
- 「これってどう見える?」と、気軽に相談できる空気をつくる
こうした小さな対話の積み重ねが、価値観のズレを埋め、誤解や炎上を防ぐ大きな力になります。
世代や立場を超えた“学び合い”ができる組織は、デザインに強い組織でもあります。
最後に
私たちも、すべての業界・文化・背景に精通しているわけではありません。
ビジネスにおいて「誰にとっても完全にやさしい表現」を追求するのは、正直に言うと難しいです。
それでも、これまで多くのお客様から学び、さまざまな価値観に触れながら、表現のアップデートを重ねてきました。
今回の記事を読んで、
「うちのSNS運用、改めて見直してみようかな」
「社内で価値観を話し合う時間をつくってみようかな」
と感じていただけたなら、とても嬉しく思います。
これからも、“より安全で、より伝わるデザイン”についてブログでお伝えできたらと思います。